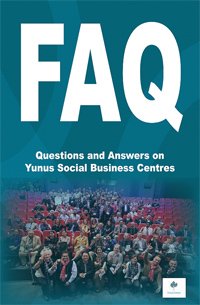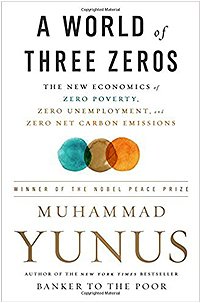ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü«Ķ▓¦Õø░ÕĢÅķĪī
ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü«Ķ▓¦Õø░ÕĢÅķĪī
’╝łŃā”ŃāīŃé╣µĢֵijŃü½ŃéłŃéŗ’╝ē
Õ╗║ÕøĮõ╗źµØźŃĆüŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü»õĖ¢ńĢīŃü¦µ£ĆŃééĶ▓¦ŃüŚŃüäÕøĮŃü«õĖĆŃüżŃü©ŃüŚŃü”ń¤źŃéēŃéīŃéŗµ¦śŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé õ║║ÕÅŻķüÄÕ»åŃĆüµ┤¬µ░┤ŃĆüµŻ«µ×Śõ╝ɵÄĪŃĆüµĄĖķŻ¤ŃĆüÕ£¤ÕŻīµ×»µĖćŃĆüĶć¬ńäČńüĮÕ«│Ńü©ŃüäŃüŻŃü¤ķüÄķģĘŃü¬ńö¤µ┤╗ńÆ░ÕóāŃü©Ńü«µł”ŃüäŃüīŃüÜŃüŻŃü©ńČÜŃüäŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ŃüŚŃüŗŃüŚń¦üŃü¤ŃüĪŃü»ŃĆü Ķ▓¦Õø░Ńü©ŃüØŃü«Ķ¦Żµ▒║µ│ĢŃü½ķ¢óŃüÖŃéŗµ¢░ŃüŚŃüäĶĆāŃüłµ¢╣ŃéÆķĆ▓ŃéōŃü¦ÕÅŚŃüæÕģźŃéīŃéīŃü░ŃĆüĶ¦Żµ▒║Ńü»ÕÅ»ĶāĮŃüĀŃü©ĶĆāŃüłŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ń¦üŃü¤ŃüĪŃüīµŖ▒ŃüłŃü”ŃüäŃéŗÕĢÅķĪīŃü½ŃüżŃüäŃü”ŃĆüķüŗÕæĮŃéäĶć¬ńäČŃéäńź×µ¦śŃéÆķØ×ķøŻŃüÖŃéŗŃüōŃü©Ńü»Ńü¦ŃüŹŃéŗŃü©Ńü»µĆØŃüäŃüŠŃüøŃéōŃĆé ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü«ń£¤Ńü«ÕĢÅķĪīŃü»ŃĆüĶć¬ńäČńüĮÕ«│Ńü¦Ńü»Ńü¬ŃüäŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé ń£¤Ńü«ÕĢÅķĪīŃü»ŃĆüõ║║ķ¢ōŃüīõĮ£ŃéŖÕć║ŃüŚŃü¤Õ║āń»äÕø▓Ńü½ŃéÅŃü¤ŃéŗĶ▓¦Õø░Ńü¦ŃüÖŃĆé
Õ«ēÕģ©ŃüĖŃü«µŁ®Ńü┐
ŃéĄŃéżŃé»ŃāŁŃā│ŃĆüµ┤¬µ░┤ŃĆüķ½śµĮ«Ńü»ŃĆüõ╗¢Ńü«ÕøĮŃĆģŃü¦ŃééĶĄĘŃüōŃéŖŃüŠŃüÖŃĆé Ńü╗Ńü©ŃéōŃü®Ńü«ÕĀ┤ÕÉłŃĆüŃüØŃéīŃéēŃü«ńüĮÕ«│Ńü»ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü¦Ķ”ŗŃéēŃéīŃéŗµ¦śŃü¬Õż¦ŃüŹŃü¬µé▓ÕŖćŃü½Ńü»Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
Ńü¬Ńü£Ńü¬ŃéēŃĆüõ╗¢Ńü«ÕøĮŃĆģŃü»ķś▓ĶĪøµēŗµ«ĄŃéäń½ŗµ┤ŠŃü¬ÕĀżķś▓ŃéÆõĮ£ŃéīŃéŗŃü╗Ńü®ÕŹüÕłåĶŻĢń”ÅŃü¦ŃüéŃéŗŃüŗŃéēŃü¦ŃüÖŃĆé Ńé½ŃāŖŃāĆŃéäŃéżŃé«Ńā¬Ńé╣ŃĆüŃāĢŃā®Ńā│Ńé╣Ńü«µ▓│ÕĘØŃü¦ŃééŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü©ŃéłŃüÅõ╝╝Ńü¤ķ½śµĮ«ŃüīĶĄĘŃüōŃéŖŃüŠŃüÖŃüīŃĆü µĄÜµĖ½µ®¤’╝łŃüŚŃéģŃéōŃüøŃüżŃüŹ’╝ēŃéäÕ£¤µēŗŃéÆõĮ£Ńéŗõ║ŗŃü½ŃéłŃéŖŃĆüõ║║ÕæĮŃüĖŃü«ÕĮ▒ķ¤┐ŃéäĶäģÕ©üŃéƵ£ĆÕ░ÅķÖÉŃü½Ńü©Ńü®ŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü¦Ńü»ŃĆüÕżÜŃüÅŃü«Ķ▓¦Õø░Õ▒żŃüīĶć¬ÕłåķüöŃéÆÕ«łŃéŗŃü«Ńü½µ£ĆõĮÄķÖÉÕ┐ģĶ”üŃü¬Õ«ēÕģ©ŃüĢŃüłńÉåĶ¦ŻŃüÖŃéŗŃüōŃü©ŃééŃü¦ŃüŹŃü¬ŃüäŃü«Ńü½ķ¢óŃéÅŃéēŃüÜŃĆüĶ▓¦Õø░Ńéäõ║║ÕÅŻķüÄÕ»åŃü½ŃéłŃéŖŃĆüŃüĢŃéēŃü½ÕŹ▒ķÖ║Ńü¬Õ£░Õ¤¤Ńü½Ķ┐ĮŃüäŃéäŃéēŃéīŃĆüŃüØŃüōŃü¦ńö¤Ķ©łŃéÆń½ŗŃü”ŃéŗŃüÖŃü╣ŃéÆĶ”ŗŃüżŃüæŃü¢ŃéŗŃéÆÕŠŚŃü¬ŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüŹŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õĖ¢ńĢīÕ╣│ÕÆīŃéÆĶäģŃüŗŃüÖŃééŃü«
ŃüŚŃü¤ŃüīŃüŻŃü”ŃĆüĶ▓¦Õø░Ńü»ŃĆüõ║║ŃĆģŃü½ÕæĮŃéÆĶäģŃüŗŃüÖÕŹ▒ķÖ║ŃéÆõ╝┤ŃüåÕø░ķøŻŃéäõĖŹÕ╣ĖŃéÆÕ╝ĘŃüäŃéŗŃüĀŃüæŃü¦Ńü»ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé Ķ▓¦Õø░Ńü»ŃĆüõ║║ŃĆģŃüīĶć¬ÕłåŃü«ķüŗÕæĮŃéÆĶć¬ÕłåŃü¦µ▒║ŃéüŃéēŃéīŃéŗŃü©ŃüäŃüåõ║ŗŃéÆõĖŹÕÅ»ĶāĮŃü¬õ║ŗŃü¦ŃüéŃéŗŃüŗŃü«µ¦śŃü½Ķ”ŗŃüøŃü”ŃüŚŃüŠŃüåŃü¤ŃéüŃĆü õ║║Ńü«µ©®Õł®ŃéÆń®ČµźĄńÜäŃü½ÕɔիÜŃüÖŃéŗŃééŃü«Ńü¦ŃüÖŃĆé ŃüōŃü«ÕøĮŃéäõ╗¢Ńü«ÕøĮŃü¦ŃééŃĆüĶ©ĆĶ½¢Ńéäõ┐Īõ╗░Ńü«Ķć¬ńö▒ŃüīĶ┐½Õ«│ŃüĢŃéīŃéŗµÖéŃĆüŃüōŃéīŃü½ÕÅŹÕ┐£ŃüŚŃü”ŃĆüõĖ¢ńĢīńÜäŃü¬µŖŚĶŁ░ķüŗÕŗĢŃüīŃüŚŃü░ŃüŚŃü░Õ▒Ģķ¢ŗŃüĢŃéīŃüŠŃüÖŃĆé
Ķ▓¦Õø░Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ŃĆüõĖ¢ńĢīŃü«ÕŹŖÕłåŃü«õ║║Ńü«õ║║µ©®ŃüīõŠĄÕ«│ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆü ŃéÅŃéīŃéÅŃéīŃü«Ńü╗Ńü©ŃéōŃü®ŃüīķĆ▓ŃéƵ¢╣ÕÉæŃéÆÕżēŃüłŃĆüÕēŹÕÉæŃüŹŃü½ķĆ▓ŃéōŃü¦ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ÕÉīŃüśńÉåńö▒Ńü¦ŃĆüĶ▓¦Õø░Ńü»ŃĆüŃāåŃāŁŃā¬Ńé║ŃāĀŃéäÕ«ŚµĢÖÕ»Šń½ŗŃĆüµ░æµŚÅÕ»Šń½ŗŃĆüµö┐µ▓╗õĖŖŃü«Õ»Šń½ŗŃéäŃĆü µÜ┤ÕŖøŃé䵳”õ║ēŃéÆõ┐āŃüÖŃééŃü«Ńü©ŃüŚŃü”ŃüŚŃü░ŃüŚŃü░Õ╝ĢŃüŹÕÉłŃüäŃü½Õć║ŃüĢŃéīŃéŗõ╗¢Ńü«õĖ¢ńĢīŃéÆĶäģŃüŗŃüÖŃééŃü«ŃéłŃéŖŃééŃĆüõĖ¢ńĢīÕ╣│ÕÆīŃéÆŃééŃüŻŃü©ŃééĶäģŃüŗŃüÖĶäģÕ©üŃüŗŃééŃüŚŃéīŃüŠŃüøŃéōŃĆé
ÕĖīµ£øŃü«Õ¢¬Õż▒
Ķ▓¦Õø░Ńü½ŃéłŃéŖŃĆüõ║║Ńü»ÕĖīµ£øŃéÆÕż▒ŃüäŃĆüĶ欵Ü┤Ķ欵ŻäŃü½Ńü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé õĮĢŃééŃüøŃüÜŃü¤ŃüĀķüŗÕæĮŃéÆÕÅŚŃüæÕģźŃéīŃéŗŃéłŃéŖŃĆüńŖȵ│üŃéÆĶē»ŃüÅŃüÖŃéŗÕ░ÅŃüĢŃü¬ÕÅ»ĶāĮµĆ¦ŃéÆõ╝┤ŃüŻŃü¤ĶĪīÕŗĢŃéÆŃü©Ńéŗµ¢╣ŃüīŃüäŃüäŃü«Ńü¦ŃĆü õĮĢŃééŃüøŃüÜŃü½µÜ┤ÕŖøŃéƵłæµģóŃüÖŃéŗŃééŃüŻŃü©ŃééŃü¬ńÉåńö▒Ńü»ŃĆüõĮĢŃééŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé Ķ▓¦Õø░ŃüīŃĆüńĄīµĖłńÜäŃü¬ķøŻµ░æńö¤Ńü┐Õć║ŃüŚŃĆüõ║║ŃĆģŃü«ĶĪØń¬üŃéÆÕ╝ĢŃüŹĶĄĘŃüōŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
Ķ▓¦Õø░ŃüīŃĆüõ║║ŃĆģŃéäŃĆüõ╗▓ķ¢ōŃĆüÕøĮŃü«ķ¢ōŃü¦ŃĆüõĖŹĶČ│ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗĶ│ćµ║ÉŃĆüµ░┤ŃĆüõĮ£ńē®ŃéÆńö¤ńöŻŃü¦ŃüŹŃéŗÕ£¤Õ£░ŃĆüŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝õŠøńĄ”ŃĆüÕ┐ģķ£ĆÕōüŃéÆŃéüŃüÉŃüŻŃü”Ńü▓Ńü®ŃüäĶĪØń¬üŃéÆÕ╝ĢŃüŹĶĄĘŃüōŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé ŃüŖõ║ÆŃüäŃü½Ķ▓┐µśōŃéÆĶĪīŃüäŃĆüŃé©ŃāŹŃā½Ńé«Ńā╝ŃéÆńĄīµĖłńÖ║Õ▒ĢŃü½ÕģģŃü”ŃéŗĶŻĢń”ÅŃü¬ÕøĮŃĆģŃü¦Ńü»ŃĆü Ķ▓¦Õø░Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ń░ĪÕŹśŃü½µł”õ║ēŃü½Ķ©┤ŃüłŃéŗķØ×õ║║ķ¢ōńÜäŃü¬ÕøĮŃĆģŃü©µł”õ║ēŃü½Ńü¬Ńéŗõ║ŗŃü»µ╗ģÕżÜŃü½ŃüéŃéŖŃüŠŃüøŃéōŃĆé
Ńā×ŃéżŃé»ŃāŁŃé»Ńā¼ŃéĖŃāāŃāłŃü½ŃéłŃüŻŃü”õ║║ŃĆģŃüīĶ▓¦Õø░ŃüŗŃéēµŖ£ŃüæÕć║ŃéēŃéīŃéŗŃā× ŃéżŃé»ŃāŁŃé»Ńā¼ŃéĖŃāāŃāłŃü»ŃĆüÕ╣│ÕÆīŃéÆŃééŃü¤ŃéēŃüøŃéēŃéīŃéŗķĢʵ£¤Ńü½µĖĪŃéŗÕĮ▒ķ¤┐ÕŖøŃü¦ŃüÖŃĆé ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü»ŃĆüŃüØŃü«ÕŖøŃéÆńż║ŃüÖŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃü¤µ┤╗ŃüŹŃü¤õŠŗŃü¦ŃüÖŃĆé õ╗ŖµŚźŃĆüŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü»ŃĆüķØ®µ¢░ńÜäŃü¬ńżŠõ╝ÜŃü©ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣ńÜäŃü¬ĶĆāŃüłµ¢╣Ńü½ŃéłŃüŻŃü”ÕŠÉŃĆģŃü½ÕżēÕī¢ŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃĆü õĖ¢ńĢīŃü¦µ£ĆŃééĶ▓¦ŃüŚŃüäÕøĮŃü«õĖĆŃüżŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüńö¤ŃüŹŃü¤Õ«¤ķ©ōÕĀ┤Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃüōŃü«20Õ╣┤ķ¢ōŃü¦ŃĆüŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü«Ķ▓¦Õø░Õ▒żŃü«õ║║ŃĆģŃü«ńö¤µ┤╗ńÆ░ÕóāŃü»ŃĆüŃü®ŃéōŃü®Ńéōµö╣Õ¢äŃüŚŃü”ŃüäŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ńĄ▒Ķ©łŃééŃüōŃéīŃéÆńē®Ķ¬×ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ÕēŹķĆ▓Ńü«ÕģåŃüŚ
(õĖ¢ńĢīķŖĆĶĪīŃü«µ¦śŃü¬ŃĆüÕøĮķÜøńÜäŃü¬µö»µÅ┤ńĄäń╣öŃü½ŃéłŃüŻŃü”µĖ¼Õ«ÜŃüĢŃéīŃü¤)ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü«Ķ▓¦Õø░ńÄćŃü»ŃĆü 1973-74Õ╣┤Ńü»Õż¦õĮō74%Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆü1991-1992Õ╣┤Ńü»57%ŃĆü2000Õ╣┤Ńü»49%ŃĆüŃüØŃüŚŃü”2005Õ╣┤Ńü»40%ŃüĖŃü©µĖøÕ░æŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
Ķ▓¦Õø░ńÄćŃü»ŃüŠŃüĀķ½śŃüäŃüīŃĆü1Õ╣┤Ńü½1%ń©ŗÕ║”ŃüÜŃüżµĖøÕ░æŃüŚńČÜŃüæŃü”ŃüŖŃéŖŃĆü1%ŃüöŃü©Ńü½õĮĢÕŹüõĖćõ║║ŃééŃü«ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźõ║║Ńü«ńö¤µ┤╗ŃüīµźĄŃéüŃü”µö╣Õ¢äŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©ŃéÆńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü»ŃĆü2015Õ╣┤ŃüŠŃü¦Ńü½Ķ▓¦Õø░ŃéÆÕŹŖÕłåŃü½µĖøŃéēŃüÖŃü©ŃüäŃüåŃā¤Ńā¼ŃāŗŃéóŃāĀķ¢ŗńÖ║ńø«µ©ÖŃü«Ńé┤Ńā╝Ńā½ŃéÆŃĆü ķĀåĶ¬┐Ńü½ĶĪīŃüæŃü░ķüöµłÉŃü¦ŃüŹŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüĢŃéēŃü½µ│©ńø«ŃüÖŃü╣ŃüŹŃü»ŃĆüŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü«µĆźķƤŃü¬ńĄīµĖłµłÉķĢĘŃü»ŃĆüŃü╗Ńü©ŃéōŃü®µĀ╝ÕĘ«ŃéÆŃééŃü¤ŃéēŃüĢŃüÜŃü½ķüöµłÉŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗõ║ŗŃü¦ŃüÖŃĆé µēĆÕŠŚÕłåķģŹŃü«õĖŹÕ╣│ńŁēŃüĢŃéÆĶĪ©ŃüÖµī浩ÖŃü©ŃüŚŃü”õĖĆĶł¼ńÜäŃü½õĮ┐ńö©ŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃéĖŃāŗõ┐éµĢ░Ńü»ŃĆü 1995Õ╣┤Ńü½Ńü»0.30Ńü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆü2005Õ╣┤Ńü½Ńü»0.31Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆüŃü╗ŃéōŃü«ŃéÅŃüÜŃüŗŃüŚŃüŗÕżēÕī¢ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüøŃéōŃĆé
2000Õ╣┤õ╗źµØźŃĆüÕøĮµ░æŃü▓Ńü©ŃéŖŃüéŃü¤ŃéŖŃü«µēĆÕŠŚŃü»ŃĆüµ£ĆõĖŗÕ▒ż10’╝ģŃü«õ║║ŃĆģŃééŃāłŃāāŃāŚŃü«10%Ńü«õ║║ŃĆģŃééÕÉīŃüśõ╝ĖŃü│ńÄć(2.8%)Ńü¦ÕóŚÕŖĀŃüŚŃü”ŃüäŃéŗŃüōŃü©Ńü»ŃĆüµ│©ńø«Ńü½ÕĆżŃüŚŃüŠŃüÖŃĆé
µśÄńó║Ńü¬µłÉķĢĘ
Ķ▓¦Õø░Ńü«µĆźķƤŃü¬µö╣Õ¢äŃü»ŃĆüńĄīµĖłńÜäŃü¬µłÉķĢĘŃĆüķøćńö©ÕĮóÕ╝ÅŃéäńĄīµĖłµ¦ŗķĆĀŃü«ÕżēÕī¢Ńü½ńÅŠŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźńĄīµĖłŃü»710ÕääŃāēŃā½Ńü¦ŃĆüÕŹŚŃéóŃéĖŃéóŃü¦ŃéżŃā│ŃāēŃĆüŃāæŃéŁŃé╣Ńé┐Ńā│Ńü½ŃüżŃüäŃü¦3ńĢ¬ńø«Ńü¦ŃüéŃéŖŃĆü ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü«ńĄīµĖłµłÉķĢĘńÄćŃü»ŃĆü1980Õ╣┤õ╗ŻŃü»Ńü¤ŃüŻŃü¤4’╝ģŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆü2000Õ╣┤õ╗źµØźÕ╣│ÕØć5.5’╝ģŃĆü2006Õ╣┤Ńü½Ńü»6.7’╝ģŃü½ķüöŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ÕŖĀŃüłŃü”ŃĆü1980Õ╣┤õ╗ŻŃü½Ńü»1%Ńü¦ŃüéŃüŻŃü¤ÕøĮµ░æ1õ║║ÕĮōŃéŖŃü«µłÉķĢĘńÄćŃü»ŃĆüńÅŠÕ£©Ńü¦Ńü»3.5%Ńü½ÕóŚÕŖĀŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé Ķć¬ńĄ”Ķć¬ĶČ│Ńü«õŠØÕŁśÕ║”Ńü»ŃĆüÕŠÉŃĆģŃü½µĖøÕ░æŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
2005Õ╣┤Ńü½Ńü»ŃĆüńö░ĶłÄŃü«Õ£░Õ¤¤Ńü½õĮÅŃéōŃü¦ŃüäŃéŗõ║║Ńü«õĖ╗Ńü¬ÕÅÄÕģźŃüīŃĆüĶŠ▓µźŁÕŖ┤ÕāŹĶĆģŃéłŃéŖķØ×ĶŠ▓µźŁÕŖ┤ÕāŹĶĆģŃü«µ¢╣ŃüīÕżÜŃüÅŃü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ŃüØŃüŚŃü”ŃĆüõ╗ŖŃĆüGDPŃü«50’╝ģŃéÆŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣µźŁŃüīÕŹĀŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü»ŃĆüÕ£░ńÉāŃü¦ŃééŃüŻŃü©Ńééõ║║ÕÅŻÕ»åÕ║”Ńüīķ½śŃüäÕøĮŃü«’╝æŃüżŃü¦ŃüéŃéŖŃĆüõ║║ÕÅŻÕóŚÕŖĀŃüīõĖ╗Ńü¬ÕĢÅķĪīŃü¦ŃüéŃüŻŃü¤ŃüīŃĆü 1970Õ╣┤õ╗ŻŃü½Ńü»Õ╣┤Õ╣│ÕØć3’╝ģŃüĀŃüŻŃü¤õ║║ÕÅŻÕóŚÕŖĀńÄćŃüīŃĆü2000Õ╣┤Ńü½Ńü»1.5’╝ģŃü½µŖæÕłČŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ŃüōŃéīŃü»ŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃü«1.4’╝ģŃü½Ķ┐æŃüÅŃĆüŃāæŃéŁŃé╣Ńé┐Ńā│Ńü«2.5’╝ģŃéłŃéŖõĮÄŃüÅŃü¬ŃüŻŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ńö¤µ┤╗Ńü«Ķ│¬
ŃüōŃü«õ║║ÕÅŻÕóŚÕŖĀŃü«µŖæÕłČŃü»ŃĆüÕŁÉõŠøķüöŃéÆĶé▓Ńü”ŃĆüŃüŹŃüĪŃéōŃü©ŃüŚŃü¤µĢÖĶé▓µ®¤õ╝ÜŃéÆÕŁÉõŠøŃü½õĖÄŃüłŃéŗÕ«ČµŚÅŃüīÕóŚŃüłŃü”ŃüäŃéŗõ║ŗŃéƵäÅÕæ│ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃüōŃéīŃü»ŃüŠŃü¤ŃĆüõĮĢńÖŠõĖćŃééŃü«Õź│µĆ¦ŃüīÕŁÉõŠøŃéÆńöŻŃéōŃü¦ŃĆüĶé▓Ńü”ŃĆüŃüŠŃü¤ńöŻŃéōŃü¦ŃĆüŃü©ŃüäŃüåńĄéŃéÅŃéŖŃü«Ńü¬ŃüäŃéĄŃéżŃé»Ńā½ŃüŗŃéēŃü«ķ¢ŗµöŠŃéäŃĆüÕĮ╝Õź│ķüöŃüīńö¤ńöŻńÜäŃü¬õ╗Ģõ║ŗŃéÆŃüÖŃéŗõ║ŗŃü¦ŃĆüńö¤µ┤╗µ░┤µ║¢Ńü«µö╣Õ¢äŃéƵēŗÕŖ®ŃüæŃüÖŃéŗµ®¤õ╝ÜŃéÆõĖÄŃüłŃü”ŃüäŃéŗŃü©ŃüäŃüåõ║ŗŃééµäÅÕæ│ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
õ║║ÕÅŻŃü«Ńé│Ńā│ŃāłŃāŁŃā╝Ńā½
Õż¦ŃüŹŃüÅŃü»ŃāśŃā½Ńé╣Ńé▒ŃéóŃü«ÕłåķćÄŃü¦Ńü«ķĆ▓µŁ®Ńü½ŃéłŃéŖŃĆüõ║║ÕÅŻÕóŚÕŖĀŃüīµŖæŃüłŃéēŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ÕŁÉõŠøķüöŃü«ńö¤ÕŁśńÄćŃüīõĖŖŃüīŃéŗŃü½ŃüżŃéīŃü”ŃĆü Ķ”¬Ńü¤ŃüĪŃü»ŃĆüŃééŃü»Ńéä2õ║║Ńü«ŃüōŃü®ŃééŃéÆÕż¦õ║║Ńü½Ķé▓Ńü”ŃéŗŃü¤Ńéü5ŃĆ£6õ║║Ńü«ÕŁÉõŠøŃéÆńöŻŃéĆÕ┐ģĶ”üŃüīŃü¬ŃüäŃü©ĶĆāŃüłŃéēŃéīŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃéŖŃĆüÕ«ČµŚÅĶ©łńö╗Ńü½Ķć¬õ┐ĪŃüīµīüŃü”ŃéŗŃéłŃüåŃü½Ńü¬ŃüŻŃü¤Ńü«Ńü¦ŃüÖŃĆé 1990Õ╣┤õ╗ŻŃü¦ŃĆüÕć║ńö¤ÕēŹŃü½ŃāśŃā½Ńé╣Ńé▒ŃéóŃéÆÕÅŚŃüæŃéŗŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü«µ»ŹĶ”¬Ńü«Õē▓ÕÉłŃü»ŃĆü2ÕĆŹŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ńĄÉµ×£Ńü«õĖĆķā©ŃéÆń┤╣õ╗ŗŃüÖŃéŗŃü©ŃĆü1990ŃĆ£2006Õ╣┤Ńü«ķ¢ōŃü½ŃĆüŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü«Õ╣╝ÕģÉŃü«µŁ╗õ║ĪńÄćŃü»ŃĆü ÕŹŖÕłåõ╗źõĖŗŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤’╝ł1000õ║║Ńü«ÕŁÉõŠøŃü«ŃüåŃüĪŃĆü100õ║║ŃüĀŃüŻŃü¤Ńü«Ńüī41õ║║Ńü½µĖøÕ░æ’╝ēŃĆé
ÕŖĀŃüłŃü”ŃĆü5µŁ│õ╗źõĖŗŃü«Õ╣╝ÕģÉŃü«µŁ╗õ║ĪńÄćŃü»1000õ║║ŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃü¦Ńü»87õ║║ŃĆüŃāæŃéŁŃé╣Ńé┐Ńā│Ńü¦Ńü»98õ║║ŃüĀŃüīŃĆü ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü¦Ńü»52õ║║Ńü¦ŃüÖŃĆé
ŃāśŃā½Ńé╣Ńé▒ŃéóŃü©Õ╣│ÕØćõĮÖÕæĮ
2005Õ╣┤Ńü«µ«ĄķÜÄŃü¦ŃĆüµ£ĆĶ▓¦Õø░Õ▒żŃü«õĖ¢ÕĖ»20%Ńü«ÕåģŃĆüĶ║½õĮōŃü½ÕŹüÕłåŃü¬ÕģŹń¢½ŃüīÕéÖŃéÅŃüŻŃü”ŃüäŃéŗ1µŁ│ÕģÉŃü«Õē▓ÕÉłŃü»ŃĆü ŃéżŃā│ŃāēŃü«21%ŃĆüŃāæŃéŁŃé╣Ńé┐Ńā│Ńü«23%Ńü½Õ»ŠŃüŚŃĆüŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü»50%Ńü¦ŃüÖŃĆé 81%Ķ┐æŃüÅŃü«ÕŁÉõŠøķüöŃüīŃü»ŃüŚŃüŗŃü«õ║łķś▓µÄźń©«ŃéÆÕÅŚŃüæŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃü¦Ńü«Õē▓ÕÉłŃü»58%Ńü¦ŃüÖŃĆé
ńÖ║Ķé▓ŃüīµŁóŃüŠŃüŻŃü¤ÕŁÉõŠøķüöŃü«Õē▓ÕÉłŃü»ŃĆü1985-86Õ╣┤Ńü»Ńü╗Ńü╝70%ŃüŠŃü¦ŃüéŃéŖŃĆü2004Õ╣┤Ńü½Ńü»43%Ńü½ŃüŠŃü¦õĮÄõĖŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüÕŁÉõŠøŃü«µĀäķżŖÕż▒Ķ¬┐Ńü»õŠØńäČŃü©ŃüŚŃü”µĘ▒Õł╗Ńü¬ÕĢÅķĪīŃü¦ŃüÖŃĆé
Õ╣│ÕØćÕ»┐ÕæĮŃü«ńĄ▒Ķ©łŃü»ŃĆü1990Õ╣┤õ╗ŻÕēŹÕŹŖŃü»56µŁ│õ╗śĶ┐æŃü¦Ńü╗Ńü©ŃéōŃü®ÕżēÕī¢ŃüŚŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆüŃüØŃü«ÕŠīõĖŖµśćŃéÆÕ¦ŗŃéüŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé 2006Õ╣┤ŃüŠŃü¦Ńü½Ńü»ŃĆüÕ╣│ÕØćÕ»┐ÕæĮŃüī65µŁ│Ńü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆéÕź│µĆ¦Ńü«Õ╣│ÕØćÕ»┐ÕæĮŃüīńöʵƦŃéłŃéŖõĮÄŃüäŃü©ŃüäŃüåńĢ░ÕĖĖŃü¬ńŖȵģŗŃü»ŃüżŃüäŃü½ķĆåĶ╗óŃüŚŃĆüÕź│µĆ¦Ńü»65µŁ│ŃĆüńöʵƦŃü»64µŁ│Ńü©ŃüäŃüåńŖȵ│üŃü¦ŃüÖŃĆé
µĢÖĶé▓Ńü«µ®¤õ╝Ü
ÕŁÉõŠøķüöŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗµĢÖĶé▓Ńü«µ®¤õ╝ÜŃééŃüŠŃü¤ŃĆüµö╣Õ¢äŃüĢŃéīŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé Õ░ÅÕŁ”µĀĪŃü«µ£ĆńĄéÕŁ”Õ╣┤’╝łŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü»5Õ╣┤ńö¤Ńüīµ£ĆńĄéÕŁ”Õ╣┤’╝ēŃéÆÕŹÆµźŁŃüÖŃéŗŃüōŃü®ŃééŃü«Õē▓ÕÉłŃü»ŃĆü 1990Õ╣┤Ńü½Ńü»49’╝ģŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆü2004Õ╣┤Ńü½Ńü»74’╝ģŃü½ÕóŚÕŖĀŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé ĶŁśÕŁŚńÄćŃü»ŃĆü1981Õ╣┤Ńü½Ńü»Ńü¤ŃüŻŃü¤26’╝ģŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆü1990Õ╣┤Ńü½Ńü»34’╝ģŃü½ŃĆü2002Õ╣┤Ńü½Ńü»41’╝ģŃü½µö╣Õ¢äŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŹŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé1990Õ╣┤õ╗ŻŃü½Ńü»ŃĆüõĖŁÕŁ”µĀĪŃü½Õć║ÕĖŁŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕŁÉõŠøķüöŃü«µĢ░Ńü»ŃĆü3ÕĆŹŃü½Ńü¬ŃéŖŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ńÅŠÕ£©ŃĆüõĖŁÕŁ”µĀĪŃü½Õ£©ń▒ŹŃüŚŃü”ŃüäŃéŗńö¤ÕŠÆµĢ░Ńü»ŃĆüńöĘÕŁÉŃéłŃéŖÕź│ÕŁÉŃü«µ¢╣ŃüīÕżÜŃüäńŖȵ│üŃü¦ŃüÖŃĆé ŃüōŃéīŃü»ŃĆü1990Õ╣┤õ╗ŻÕłØķĀŁŃĆüõĖŁÕŁ”µĀĪŃü½Õ£©ń▒ŹŃüÖŃéŗńöĘÕŁÉŃü«µĢ░ŃüīÕź│ÕŁÉŃü«3ÕĆŹŃü¦ŃüéŃüŻŃü¤ŃüōŃü©ŃéÆĶĆāŃüłŃéŗŃü©ŃĆüÕŹŚŃéóŃéĖŃéóŃü½µ»öķĪ×Ńü«Ńü¬ŃüäÕż¦ÕżēŃü¬ÕüēµźŁŃü¦ŃüÖŃĆé
õ┐ØķÖ║ĶĪøńö¤
ŃéĘŃé¦Ńā½Ńé┐Ńā╝Ńü«Ķ│¬ŃéäÕ¤║µ£¼ńÜäŃü¬Õģ¼ĶĪåĶĪøńö¤Ńü©ķĆÜõ┐Īµēŗµ«ĄŃéÆÕł®ńö©Ńü¦ŃüŹŃéŗńÆ░ÕóāŃü»ŃĆüµ£ĆĶ┐æŃü¦Ńü»ŃüÖŃü╣Ńü”ÕŹüÕłåŃü½µö╣Õ¢äŃüĢŃéīŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ĶŹēĶæ║ŃüŹÕ▒ŗµĀ╣Ńü«Õ«ČŃü¦µÜ«ŃéēŃüŚŃü”ŃüäŃéŗÕ«ČÕ║ŁŃü«Õē▓ÕÉłŃüīŃĆü2000Õ╣┤Ńü½Ńü»Õģ©õĮōŃü«18’╝ģŃü¦ŃüŚŃü¤ŃüīŃĆü 2005Õ╣┤ŃüŠŃü¦Ńü½7’╝ģŃüŠŃü¦õĮÄõĖŗŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
Õģ¼ĶĪåĶĪøńö¤ÕÉæõĖŖŃéŁŃāŻŃā│ŃāÜŃā╝Ńā│Ńü½ŃéłŃéŖŃĆü2000Õ╣┤Ńü½Ńü»54’╝ģŃüĀŃüŻŃü¤Õ«ēÕģ©Ńü¬ŃāłŃéżŃā¼Ńü«Õē▓ÕÉłŃüī71’╝ģŃü½ŃüŠŃü¦ÕÉæõĖŖŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé µÉ║ÕĖ»ķø╗Ķ®▒Ńü«ńÖ╗ÕĀ┤Ńü½ŃéłŃéŖŃĆü2000Õ╣┤Ńü½2’╝ģŃüĀŃüŻŃü¤ķø╗Ķ®▒ŃéĄŃā╝ŃāōŃé╣Ńü«Õł®ńö©ĶĆģŃü«õ║║ÕÅŻµ»öńÄćŃüīŃĆü14’╝ģŃüĖŃü©õĖŖµśćŃüŚŃüŠŃüŚŃü¤ŃĆé
ńüĮÕ«│Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕ«łŃéŖ
ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü¦Ńü»ŃĆüĶć¬ńäČńüĮÕ«│Ńü«ŃéĘŃā¦ŃāāŃé»Ńü½µīüŃüĪŃüōŃü¤ŃüłŃéŗĶāĮÕŖøŃüīŃĆüÕŹüÕłåŃü½ķ½śŃüŠŃüŻŃü”ŃüŹŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé 1998Õ╣┤Ńü½Ńü▓Ńü®Ńüäµ┤¬µ░┤ŃüīĶĄĘŃüōŃéŖŃĆüÕøĮµ░æõĖĆõ║║ÕĮōŃü¤ŃéŖŃü«GDPŃéÆµĆźĶÉĮŃüĢŃüøŃüŠŃüŚŃü¤ŃüīŃĆü 2004Õ╣┤Ńü½ÕÉīµ¦śŃü«µ┤¬µ░┤ŃüīĶĄĘŃüōŃüŻŃü”ŃééŃĆüńĄīµĖłµłÉķĢĘŃü½Ńü╗Ńü©ŃéōŃü®ÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆõĖÄŃüłŃüŠŃüøŃéōŃü¦ŃüŚŃü¤ŃĆé
ŃüōŃü«ńüĮÕ«│Ńü½Õ»ŠŃüÖŃéŗÕø×ÕŠ®ÕŖøŃü«ÕÉæõĖŖŃü»ŃĆüÕżÜµ¦śÕī¢ŃüŚŃü¤ńĄīµĖłŃü©ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü«Ķć│ŃéŗµēĆŃü½µĢ┤ÕéÖŃüĢŃéīŃü¤µŚ®µ£¤ĶŁ”ÕĀ▒ŃéĘŃé╣ŃāåŃāĀŃéäŃéĄŃéżŃé»ŃāŁŃā│Ńü«ķü┐ķøŻµēĆŃéÆÕɽŃéĆńĘŖµĆźÕ»ŠÕ┐£ĶāĮÕŖøŃü«ÕÉæõĖŖŃü½ĶĄĘÕøĀŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé 1980Õ╣┤ŃüŗŃéē2004Õ╣┤Ńü«ķ¢ōŃü½ŃĆüõ║║ķ¢ōķ¢ŗńÖ║µīćµĢ░’╝łHDI:the Human Development IndexŃĆüńÖ║Õ▒ĢķĆöõĖŖÕøĮŃü«ńö¤µ┤╗µ░┤µ║¢ŃéƵĖ¼Ńéŗµī浩ÖŃü©ŃüŚŃü”Õ║āŃüÅńö©ŃüäŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗ’╝ēŃü»ŃĆüŃéżŃā│ŃāēŃü¦Ńü»39’╝ģŃĆüŃé╣Ńā¬Ńā®Ńā│Ńé½Ńü¦Ńü»16’╝ģŃü¦ŃüÖŃüīŃĆüŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü¦Ńü»45’╝ģŃü½ŃüŠŃü¦ÕóŚÕŖĀŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé 2004Õ╣┤Ńü«ÕøĮµ░æõĖĆõ║║ÕĮōŃü¤ŃéŖŃü«GDPŃü»ŃĆüŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü©µ»öĶ╝āŃüŚŃü”ŃéżŃā│ŃāēŃüī68’╝ģŃĆüŃé╣Ńā¬Ńā®Ńā│Ńé½Ńüī200’╝ģõ╗źõĖŖķ½śŃüäŃü½Ńééķ¢óŃéÅŃéēŃüÜŃĆüŃü¦ŃüÖŃĆé
*µ│©ķćł
ŃĆĆõ║║ķ¢ōķ¢ŗńÖ║µīćµĢ░(HDI’╝Üthe Human Development Index)’╝Üõ║║ŃĆģŃü«ńö¤µ┤╗Ńü«Ķ│¬ŃéäńÖ║Õ▒ĢÕ║”ÕÉłŃüäŃéÆńż║ŃüÖµī浩Ö
ÕøĮķÜøńżŠõ╝ÜŃüĖŃü«Õ┐£ńö©
ŃüōŃéīŃéēŃü«µĢ░ÕŁŚŃüīńż║ŃüÖµ¦śŃü½ŃĆüŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü«Ķ▓¦Õø░ÕĢÅķĪīŃü»µö╣Õ¢äŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃüīŃĆüĶ¦Żµ▒║Ńü½Ńü»Ńü╗Ńü®ķüĀŃüäńŖȵģŗŃü¦ŃüÖŃĆé ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃü»µ£¬ŃüĀŃü½õĖ¢ńĢīŃü¦µ£ĆŃééĶ▓¦ŃüŚŃüäÕøĮŃü«õĖĆŃüżŃü¦ŃüéŃéŖŃĆü õĮĢÕŹāõĖćõ║║Ńü«õ║║ŃĆģŃüīŃĆüńö¤ÕŁśŃü¦ŃüŹŃéŗµ£ĆõĮÄķÖÉŃéÆŃéäŃüŻŃü©ĶČģŃüłŃéŗń©ŗÕ║”Ńü«µ░┤µ║¢Ńü¦ńö¤µ┤╗ŃéÆŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé ŃüŚŃüŗŃüŚŃĆüńżŠõ╝ÜńÜäŃü¬ÕŗĢÕÉæŃéäńĄīµĖłńÜäŃü¬ÕŗĢÕÉæŃü»ŃĆüŃüäŃüäµ¢╣ÕÉæŃüĖķĆ▓ŃéōŃü¦ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃüīńø┤ķØóŃüŚŃü”ŃüäŃéŗµīæµł”Ńü©ŃüØŃü«µ®¤õ╝ÜŃü»ŃĆü õĖ¢ńĢīŃü«ńÖ║Õ▒ĢķĆöõĖŖÕøĮŃü«ÕżÜŃüÅŃü½Õģ▒ķĆÜŃüÖŃéŗŃüäŃüÅŃüżŃüŗŃü«ķćŹĶ”üŃü¬ŃāåŃā╝Ńā×ŃéÆńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
1’╝ĵłÉķĢĘŃü«µ®¤õ╝ÜŃéƵÄóŃéŗµÖéŃü½ŃĆüŃüØŃü«Õ£░Õ¤¤Ńü©õĖ¢ńĢīŃü½ŃüŖŃüæŃéŗŃüØŃü«ÕøĮŃü«µĮ£Õ£©ńÜäŃü¬ÕĮ╣Õē▓ŃéÆÕłåµ×ÉŃüŚŃü¬ŃüīŃéēŃĆüńÖ║Õ▒ĢŃü½ŃüżŃüäŃü”µł”ńĢźńÜäŃü½ĶĆāŃüłŃéŗÕ┐ģĶ”üµĆ¦
2’╝ÄĶ▓¦ŃüŚŃüäÕøĮŃĆģŃü½Õ»ŠŃüÖŃéŗõ╝صē┐ŃĆüÕø║իܵ”éÕ┐ĄŃĆüõ╗«Ķ¬¼ŃéäŃüØŃéīŃü½Õ¤║ŃüźŃüÅķÜŻÕøĮŃü©Ńü«ķ¢óõ┐éŃéÆÕģŗµ£ŹŃüÖŃéŗÕ┐ģĶ”üµĆ¦
3’╝ĵŖ▒ŃüłŃü”ŃüäŃéŗÕĢÅķĪīŃüĀŃüæŃü¦Ńü»Ńü¬ŃüÅŃĆüÕøĮŃü©ÕøĮµ░æŃü«µĮ£Õ£©ńÜäŃü¬ÕŖøŃéÆŃééĶ”ŗµźĄŃéüŃéŗŃĆüµ¢░ŃüŚŃüÅŃü”ń®ŹµźĄńÜäŃü¬ŃĆüķ¢ŗńÖ║ŃüĖŃü«ŃéóŃāŚŃāŁŃā╝ŃāüŃéÆĶ”ŗŃüżŃüæŃéŗÕ┐ģĶ”üµĆ¦
4’╝ÄķĆÜÕĖĖŃü»µö┐Õ║£Ńü½ŃéłŃüŻŃü”Ķ¦Żµ▒║ŃüĢŃéīŃéŗŃü╣ŃüŹŃü©ĶĆāŃüłŃéēŃéīŃü”ŃüäŃéŗŃĆüńżŠõ╝ÜńÜäŃĆüńĄīµĖłńÜäŃü¬ÕĢÅķĪīŃü½ŃéĮŃā╝ŃéĘŃāŻŃā½ŃāōŃéĖŃāŹŃé╣Ńüī Ńü®Ńü«ŃéłŃüåŃü½ÕĮ╣Ńü½ń½ŗŃüżŃüōŃü©ŃüīŃü¦ŃüŹŃéŗŃüŗŃĆüĶĆāŃüłŃéŗÕ┐ģĶ”üµĆ¦
ŃüōŃéīŃéēŃü«ŃéóŃéżŃāćŃü»ŃĆüŃāÉŃā│Ńé░Ńā®ŃāćŃéĘŃāźŃüĀŃüæŃü¦Ńü¬ŃüÅõĖ¢ńĢīõĖŁŃü«Ķ▓¦Õø░Ńü½Õ¢śŃüäŃü¦ŃüäŃéŗõ╗¢Ńü«ÕżÜŃüÅŃü«ÕøĮŃĆģŃü½Õ»ŠŃüŚŃü”ŃééŃĆü Ķ▓¦Õø░ŃüīõĖÄŃüłŃéŗÕĮ▒ķ¤┐ŃéÆĶ╗ĮµĖøŃü¦ŃüŹŃéŗŃü©ŃüäŃüåÕĖīµ£øŃéÆńż║ŃüŚŃü”ŃüäŃüŠŃüÖŃĆé
ńĘ©ķøåĶ©ś’╝ÜĶ”üńé╣Ńü»ŃĆüŃāĀŃāÅŃā×ŃāēŃā╗Ńā”ŃāīŃé╣µĢֵijŃü«ĶæŚµøĖŃĆīĶ▓¦Õø░Ńü«Ńü¬ŃüäõĖ¢ńĢīŃéÆÕēĄŃéŗŃĆŹŃüŗŃéēµÄĪńö©ŃĆé
ĶæŚõĮ£µ©®Ńü»ŃĆüPublic AffairsŃü½ÕĖ░Õ▒×’╝ł2007Õ╣┤’╝ēŃĆéÕć║ńēłńżŠŃü«Ķ©▒ÕÅ»ŃéÆÕŠŚŃü”ÕåŹńēłŃĆé